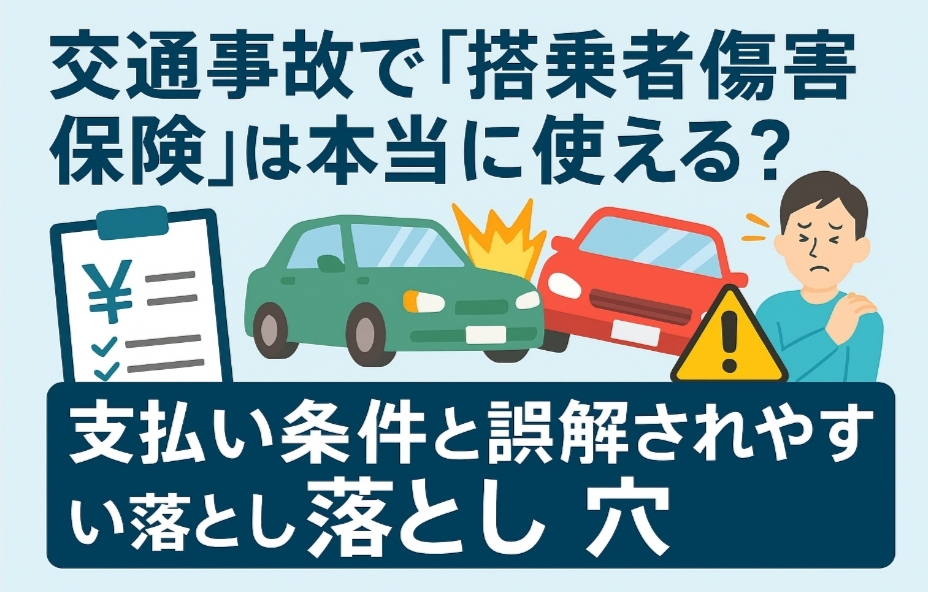こんにちは! タクシードライバー歴7年、70歳のヤヌスです。
「交通事故に遭っても、搭乗者傷害保険があるから安心」
そんな声をよく聞きます。確かにこの保険は、事故の過失に関係なく、契約車両に乗っていた人がケガをした場合に定額で保険金が支払われるという仕組みです。
つまり、加害者でも被害者でも、契約車両に乗っていた人なら対象になる。
この「過失に関係なく支払われる」という点が、安心材料として語られる理由です。
しかし、実際には「思ったより支払われない」「請求できると思っていたのに対象外だった」というケースも少なくありません。
この記事では搭乗者傷害保険の実態に迫ります。
支払い条件は意外と厳しい?「定額払い」の落とし穴
「定額払い」は誤解されやすいと言えます。
実際の支払いは「治療費」ではなく「定額の一時金」
搭乗者傷害保険は、医療費を補償するものではありません。
支払われるのは、あらかじめ定められた「傷害一時金」「入院日額」「通院日額」などの定額給付です。
たとえば:
– 骨折 → 一時金10万円
– 入院10日 → 日額5,000円 × 10日 = 5万円
– 通院20日 → 日額3,000円 × 20日 = 6万円
このように、 実際の治療費や損害額とは関係なく、定額で支払われるため、「思ったより少ない」と感じる人も多いのです。
支払い対象になる「傷害の定義」が意外と狭い
保険会社によっては、打撲・捻挫・むち打ちなどの軽傷は対象外になることもあります。
また、診断書に「異常なし」と書かれてしまうと、保険金が支払われないケースも。
つまり、事故直後に病院へ行っても、診断内容によっては「保険対象外」とされる可能性があるのです。
よくある誤解「搭乗者傷害保険で全部カバーできる」は危険
搭乗者傷害保険には限界があります。
搭乗者傷害保険は「補助的な保険」である
この保険は、あくまで自賠責保険や人身傷害保険の補助的な位置づけです。
メインの補償は「人身傷害保険」や「対人賠償保険」であり、搭乗者傷害保険は「定額の上乗せ」や「慰謝料の補填」として使われるのが本来の役割です。
「搭乗者傷害だけで十分」と思っていると損をする
特に、人身傷害保険を外して搭乗者傷害だけにしている契約者は要注意です。
事故の損害額が大きくなった場合、定額給付では到底足りず、自己負担が発生する可能性が高いです。
事故後に「使えるかどうか」を確認するポイント
事故前に保険内容を確認してよく理解しておくことは保険の基本です。
保険証券の「傷害保険金額」「日額給付額」をチェック
事故後に慌てないためにも、事前に以下を確認しておきましょう:
– 傷害一時金はいくらか?(例:10万円)
– 入院日額はいくらか?(例:5,000円)
– 通院日額はいくらか?(例:3,000円)
– 対象となる傷害の定義は?(例:骨折・脱臼・打撲など)
保険会社への連絡は「診断書を取ってから」がベスト
事故後すぐに保険会社へ連絡するのも大切ですが、診断書がないと支払い判断ができないため、まずは病院で診断を受けることが優先です。
診断書の内容が「異常なし」だと、保険金が支払われない可能性もあるため、症状がある場合は医師にしっかり伝えることが重要です。
関連記事:もらい事故でも保険が下りない?過失ゼロでも泣き寝入りする理由|制度の盲点と対策
まとめ|搭乗者傷害保険は「使い方次第」で価値が変わる
搭乗者傷害保険は、事故時の安心材料として有効ですが、その支払い条件や補償範囲を誤解していると、思わぬ損失につながることもあります。
– 定額給付であること。
– 軽傷は対象外になることがあること。
– メイン補償ではなく補助的な保険であること。
これらを理解したうえで、人身傷害保険との併用や契約内容の見直しを行うことで、本当に「安心できる保険設計」が可能になります。
事故はいつ起こるかわかりません。 だからこそ、保険の中身を理解しておくことが、損しない第一歩なのです。
この記事が役立ったと思う人は、まだ搭乗者傷害保険の実態をよく知らない人に、是非この記事を読むことをお勧めください。