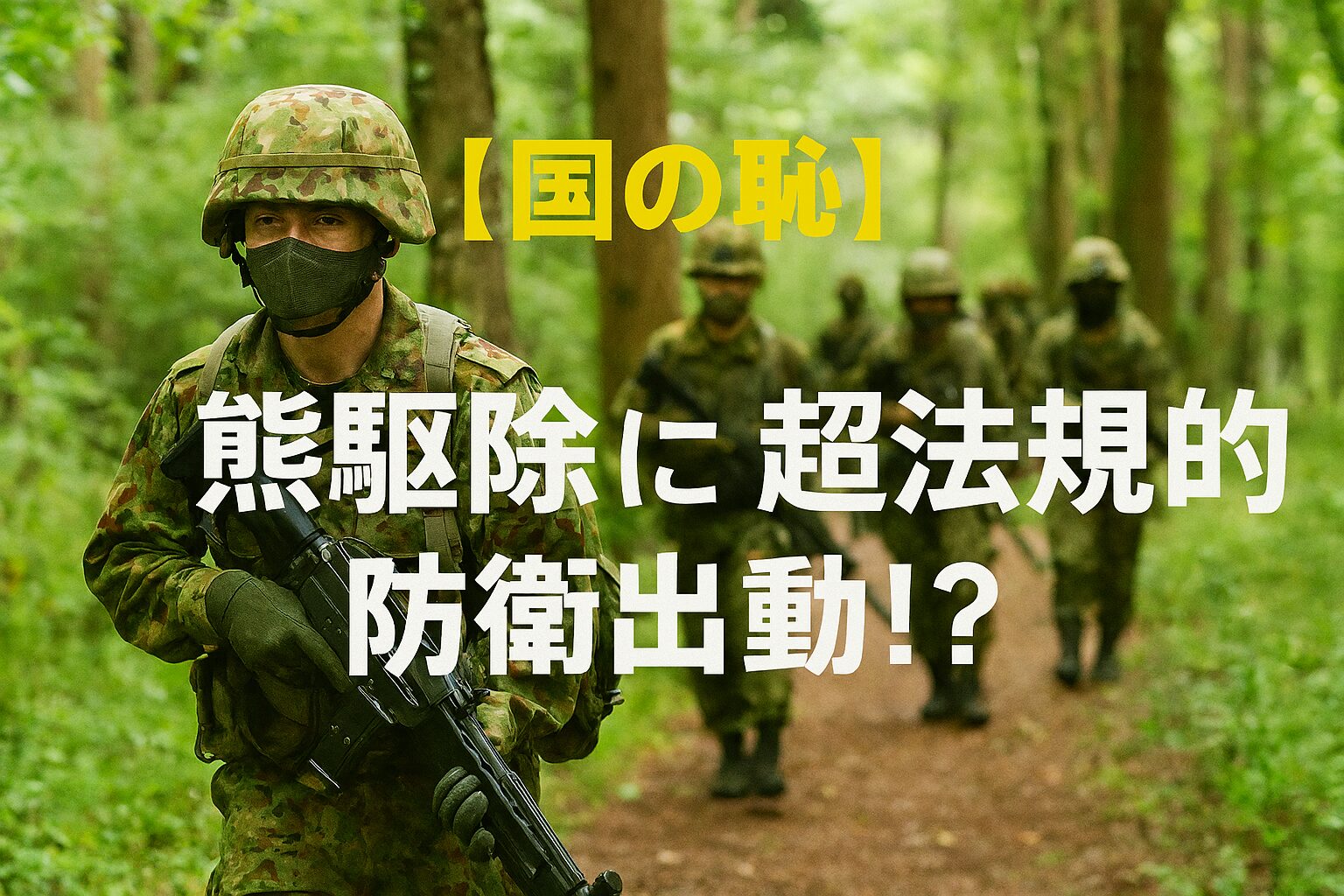こんにちは、ヤヌスです。
秋田県知事の要請を受けて始まった自衛隊によるクマ対策への派遣。しかし、その任務は箱わなの設置補助といった「後方支援」に留まり、肝心のクマの駆除、すなわち「撃つ」役割は担えません。
この状況に対し、元陸自1佐の佐藤正久氏が指摘したのが、クマが凶暴化し大量出没した場合の「超法規的措置」としての防衛出動の可能性です。これは、日本の危機管理において、極めて異様な、そして恥ずべき事態です。
なぜ、一国の自衛隊が「災害派遣」で人里に出動しながら、住民の命を守るために銃を撃てないのか? そして、なぜ「平時の獣害対策」に、「国の存立を脅かす事態」を想定した戦時の法理を語らねばならないのか?
本記事では、この異常事態の裏側にある、長年にわたり自衛隊と警察の権限を縛り続けた行政と政治の「法整備の怠慢」を徹底的に批判します。
この記事でわかること(法整備の怠慢が招いた危機):
- ・自衛隊が「災害派遣」でクマを撃てない、自衛隊法の構造的な制約。
- ・「超法規的措置としての防衛出動」という言葉が示す、行政の法整備放棄。
- ・「ガバメントハンター」制度のコスト回避が、最終的に「法的な無法状態」を招いたツケ。
- ・警察官のライフル駆除開始は、根本問題の解決になっていない理由。
1. 自衛隊派遣の異常性:「後方支援」と「防衛出動」の間の大きな溝
自衛隊が後方支援に留まり、しかも「超法規的措置」という言葉が飛び出す背景には、自衛隊法の根本的な限界があります。
1-1. 自衛隊法第83条(災害派遣)の限界
自衛隊がクマ対策に出動しているのは「災害派遣」の枠組みです。この枠組みでは、武器の使用は「自己または他の隊員、民間人に対する危害を避けるための緊急避難」に限られます。つまり、凶暴なクマを積極的に「索敵して駆除する」という本来の獣害対策の役割は、法的に許されていません。
クマの脅威が「災害」と認識されながら、その脅威を排除する権限が与えられていない。この法的な矛盾が、自衛隊を丸腰の「後方支援」に留めているのです。
1-2. 「防衛出動」の言葉が示す、平時法整備の極度の怠慢
佐藤氏が言及した「クマが20頭といった単位で現われた際の超法規的措置としての防衛出動」という言葉は、極めて重い意味を持ちます。防衛出動は、外部からの武力攻撃など、国の存立を脅かす事態に発令されるものです。平時の獣害対策という行政課題に対して、戦時の法理を持ち出さざるを得ないというのは、獣害対策に関する法的な枠組み作りを長年放棄してきた行政の怠慢の極みです。
国民の安全を守るための「平時における国家機関の権限」を、政治が長年にわたり明確に定義してこなかったツケが、この「超法規」という言葉に凝縮されています。
2. 「誰がクマを殺すか」問題を先送りした行政のコスト回避体質
今回の異常事態は、行政が「ガバメントハンター」などの恒久的な専門組織の設立コストを避け、責任の所在を曖昧にしてきた結果です。
2-1. 警察官によるライフル駆除開始の「場当たり的」な限界
警察庁が11月13日から、警察官によるライフル銃でのクマ駆除運用を開始することは、一見前進に見えます。しかし、警察官職務執行法4条は「狂犬、奔馬の類等」への武器使用を認めるものであり、これはあくまで「治安維持」と「緊急避難」の視点です。
警察の主な任務は駆除ではありません。自治体が駆除すべきクマを、警察に肩代わりさせるという構図は、「ガバメントハンター」という恒久的な公務員組織を設立するコストを、またもや回避し、既存組織の業務を場当たり的に拡大しているに過ぎません。根本的な解決にはつながりません。
2-2. 保護世論の忖度が「法的な空白地帯」を生んだ
記事にもある通り、クマの駆除に反対する自然保護団体や世論が根強いことが、「誰がクマを殺す役割を担うのか」という議論を先送りにさせてきました。行政や政治は、批判を恐れ、議論の「コスト」を回避し続けた結果、自衛隊も警察も猟友会も、それぞれが法的な制約や高齢化という限界に縛られる「法的な空白地帯」を生み出してしまったのです。
3. まとめ:危機管理は「超法規的措置」に頼るべきではない
平時の獣害対策に「防衛出動」や「超法規的措置」という言葉が飛び交うのは、日本の危機管理体制における法整備の極度の怠慢を示す、国の恥であると言わざるを得ません。
国民の命と財産を守るための国家機関の活動は、「超法規」という曖昧で政治的な言葉ではなく、明確な法律に基づいているべきです。「ガバメントハンター制度」の創設をはじめ、自衛隊法、警察官職務執行法、鳥獣保護管理法の抜本的な改正は、もはや待ったなしの状況です。
私たちは、この行政と政治の怠慢を許さず、自分の安全と生活は、自分の戦略的な行動と備えで守るべきです。
関連性の高い危機管理記事
この「法整備の怠慢」と「行政の構造的欠陥」を深掘りする以下の記事もぜひ合わせてご確認ください。