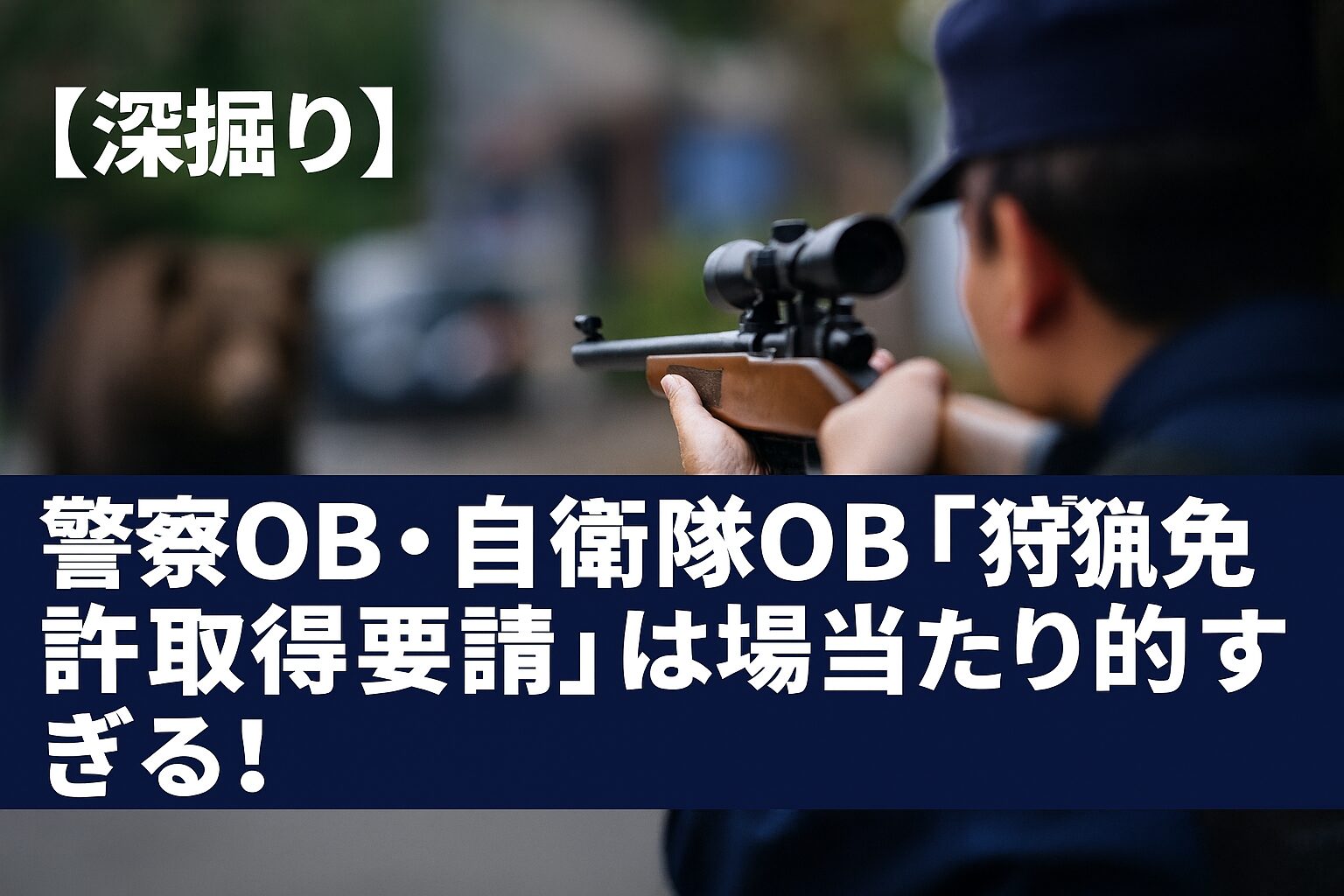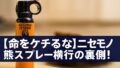こんにちは、ヤヌスです。
クマによる人身被害の深刻化を受け、環境省が自衛隊OBの隊友会に加え、新たに警察OBにも狩猟免許の取得を要請することが明らかになりました。これは、行政がクマ駆除のプロフェッショナルなリソースを切実に求めていることを示す動きです。
しかし、私たちはこのニュースを単なる「対策強化」として評価すべきではありません。この「OBへの免許取得要請」は、恒久的な対策である「ガバメントハンター制度」を公務員として確立するコストを、またもや回避し、元プロという「安価な外部リソース」に丸投げしようとする、行政の構造的なコスト回避体質の露呈であると批判します。
本記事では、この場当たり的なOB依存策の裏側にある、日本の危機管理体制の根深い問題を深掘りします。
この記事でわかること(OB要請の裏側にある構造的欠陥):
- ・警察OB・自衛隊OBへの免許要請は、なぜ「ガバメントハンター」制度のコスト回避策なのか。
- ・「免許取得」と「実戦での駆除」の間に存在する、行政が無視する重大なリスクと技術の壁。
- ・「プロのボランティア」に依存しようとする、公務員の採用・維持コストを払わない行政の構造。
- ・「市民の安全」という恒久的なコストを放置する政治の責任を、現場の元プロに転嫁する問題。
1. 警察・自衛隊OBへの要請に見る行政の「コスト回避」体質
今回の要請は、クマ駆除のプロフェッショナルな人材が必要であるという認識は正しいものの、その手法は、恒久的な仕組み構築のコストを回避しようとする行政体質の表れです。
1-1. 公務員採用コストを避け、プロのOBに丸投げする構造
自治体職員として「ガバメントハンター」を正規採用するには、公務員報酬、装備費、訓練費、退職金など、恒常的な費用が発生します。行政は、この採用コストを嫌い、「すでに経験・訓練を積んだOB」という、初期投資や継続的なコストが低い外部リソースに頼ろうとしています。これは、最も重要な「市民の安全」というコストを、またもやケチろうとする構造的な怠慢です。
1-2. 「免許取得」と「実戦」の間に存在する無視できない技術の壁
ニュース記事にもある通り、免許を持つハンターは全国に5万人以上いますが、経験の浅いハンターでは凶暴なクマの捕獲は非常に難しいとされています。警察OBや自衛隊OBが「狩猟免許」を取得しても、その免許が直ちに「市街地でライフルを確実に撃ち止められる駆除技術」に直結するわけではありません。
行政は、この技術習熟にかかるコストとリスクを無視し、OBの「危機管理に詳しい」という肩書きに頼りすぎているのです。
2. 恒久的な「ガバメントハンター」制度を阻む根本要因
警察OBへの要請は、行政が「恒久的な公務員としてのハンター制度(ガバメントハンター)」の確立を躊躇していることの裏返しであり、その躊躇の背景には根深い構造的欠陥があります。
2-1. 優秀な人材は「低リスク・高報酬」の公務員報酬を避ける
前回の記事で指摘した通り、命の危険を伴う駆除職務に対し、行政の硬直化した公務員報酬体系では、優秀な民間ハンターや若手を惹きつけることは困難です。
行政は、この報酬体系を見直してコストを増やすよりも、「免許があればボランティアで動いてくれる可能性のある元プロ」に依存するという、最も抵抗の少ない道を選んでいるのです。
2-2. 「無策の放置」のコストを最終的に現場に転嫁する構図
クマの生息域の破壊(メガソーラーなど)や、頭数管理の失敗といった「無策の放置」の責任は行政と政治にあります。その最終的な結果である「緊急駆除」のリスクと重荷を、高齢化が進む猟友会や、善意のOBという「行政の外部」に転嫁しようとする構図は、極めて無責任であると言わざるを得ません。
3. まとめ:危機管理意識の低さを示す「場当たり的依存」
警察OB・自衛隊OBへの狩猟免許取得要請は、ハンター不足という危機に対し、行政が本質的な解決策である「恒久的なガバメントハンター制度の設立」と、それに伴う「コストの増大」を避けようとする、場当たり的な外部依存の典型です。
「野生生物対策全般は環境省が鳥獣保護管理法に基づき、主導する立場にある」という発言があるように、行政が主導権を握るべき問題です。にもかかわらず、公務員としてコストを支払う責任を回避し、外部のプロに依存しようとする姿勢は、日本の危機管理意識の構造的な低さを示しています。
自分の安全と生活は、このようなコスト回避体質の行政に期待せず、自分の戦略的な行動と備えで守るべきです。
関連性の高い危機管理記事
この「行政の仕組みの欠陥」から脱却し、あなたの生活基盤を守るための以下の記事もぜひ合わせてご確認ください。