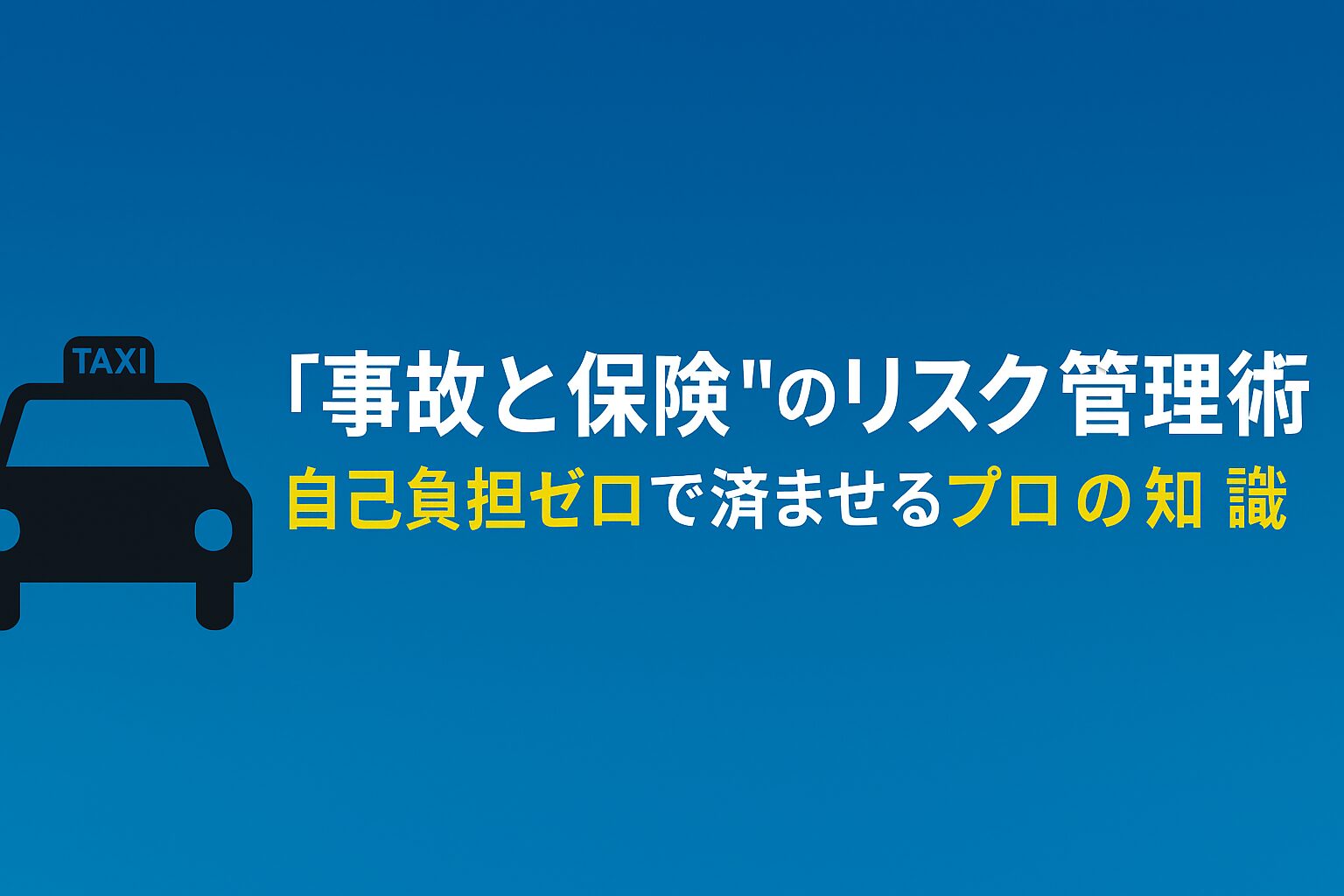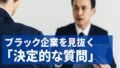こんにちは、福岡市の老舗法人タクシーで嘱託乗務員を務める現役ドライバーのヤヌスです。
タクシーという仕事で最も避けて通れないテーマが「事故」です。どれだけ安全運転を心がけても、もらってしまう事故、不運な接触は避けられません。そして、事故が起きたとき、あなたの給与やキャリアを守ってくれるのは「正しい知識」だけです。
この記事では、私が長年の乗務経験で学んだ、事故が発生した際の「初期対応の鉄則」と、ドライバーの自己負担を最小限(ゼロ)にするための「保険と会社の制度」に関するプロの知識を包み隠さずお話しします。
この記事でわかること:
・事故発生直後、警察や会社より先に「最も優先すべき初期対応の鉄則」
・タクシー運転手が最も恐れる「自己負担金」が発生するケースとゼロにする方法
・会社の保険(車両保険、対人・対物)で「給与(休業補償)」がどうなるかという現実
・プロとして備えるべき「ドラレコの映像管理」や「ドライブレコーダー任せにしない」というリスク管理術
1. 事故発生!プロが取るべき「初期対応の鉄則」3ステップ
事故後の初期対応は、後々の保険適用や自己負担額に直結します。感情的にならず、以下の3ステップを冷静に実行してください。
1-1. 【鉄則1】警察より前に、まず「乗客の安全」と「二次災害の回避」
最優先事項: 乗客の安否確認と、安全な場所への誘導。乗客に怪我があれば、必ず救護措置と病院への連絡が警察より優先です。
現場の保護: 可能な限り事故車両を動かさず、後続車への注意喚起(ハザード、三角表示板設置)を最優先。
1-2. 【鉄則2】「連絡の順序」と「報告内容の統一」
ヤヌスの手順: (1)負傷者救護 → (2)警察に通報(110番)→ (3)会社への連絡。
裏ワザ:会社への報告内容の徹底: 会社に報告する際は、感情を交えず、**「日時」「場所」「相手の名前・連絡先」「負傷者の有無」**の4点のみを正確に伝えることに集中します。
1-3. 【鉄則3】現場での「安易な発言」は絶対に避ける
最大の注意点: 現場で相手に「すみません」「私の責任です」と安易に謝罪しないこと。これは後で過失割合を決める際に不利な証拠となる可能性があります。あくまで「お怪我はありませんか」と安全確認に徹します。
2. タクシー運転手の「自己負担金」の現実と対策
法人タクシーのドライバーが最も心配するのは、事故による**「自己負担金(免責)」**の請求です。
2-1. 自己負担金が発生する主なケース
車両保険の免責: 会社の規定で、車両保険を使用した場合の**免責額(5万円〜10万円程度)**を、ドライバーが一部負担させられる場合があります。
重大な過失: 飲酒運転、信号無視、大幅な速度超過など、会社の就業規則に反する重大な過失による事故の場合、修理費用の全額または大部分を請求される可能性があります。
2-2. 自己負担をゼロにするためのプロの対策
無事故手当と相殺: 多くの優良企業では、事故を起こさなければ支給される**「無事故手当」**を貯めておき、万が一の免責額と相殺できる仕組みがあります。
優良企業を選ぶ: 【優良企業レビュー記事】で解説した通り、整備体制が強力で、免責負担のルールが明確に開示されている会社を選ぶことが、最大の自己負担対策です。
少額事故は保険を使わない: 会社の許可を得て、軽微な接触事故(数万円程度の修理)は自腹で処理する方が、評価や保険等級に影響しないため、長期的に得策となる場合があります。
3. 保険と給与の現実:事故後の休業補償はどうなるか
3-1. 事故による「休業補償」の仕組み
会社の車両が破損した場合: 修理期間中、乗務できない期間が発生します。この期間の給与補償は、会社の就業規則によります。
優良企業: 事故責任が軽度であれば、待機手当や平均賃金の一部が支払われます。
一部の会社: 責任の大小にかかわらず、一切の補償がない場合があります。
人身事故(ドライバー自身の負傷): 労災保険の対象となります。会社が加入している保険とは別に、労災の申請が最優先です。
3-2. プロのリスク管理術:映像と記録の徹底
ドラレコは万能ではない: ドライブレコーダーの映像は重要ですが、衝撃が軽微だと記録されないこともあります。
裏ワザ:写真と音声の記録: 事故現場では、スマートフォンで必ず多角的な写真(全体、ナンバープレート、損害箇所)を撮影し、可能であれば、相手との会話を録音しておく(証拠保全のため)ことが、後々の交渉で自分の身を守る最大の武器となります。
🚨 まとめ:知識は最高の防具
タクシー運転手にとって、事故は単なる不運ではなく、プロのリスク管理能力が試される瞬間です。
この記事で解説した「初期対応の鉄則」と「自己負担ゼロ戦略」は、あなたの安全と給与を守る最高の防具となります。
常に冷静に、知識を持って運行することで、事故のリスクを最小限に抑え、安定したキャリアを築いてください。
関連記事:
1.「もしも」の時に慌てない!70歳現役が教えるタクシー事故の初期対応の基礎知識